健康診断の血液検査の見方を紹介!病気の前兆についても解説
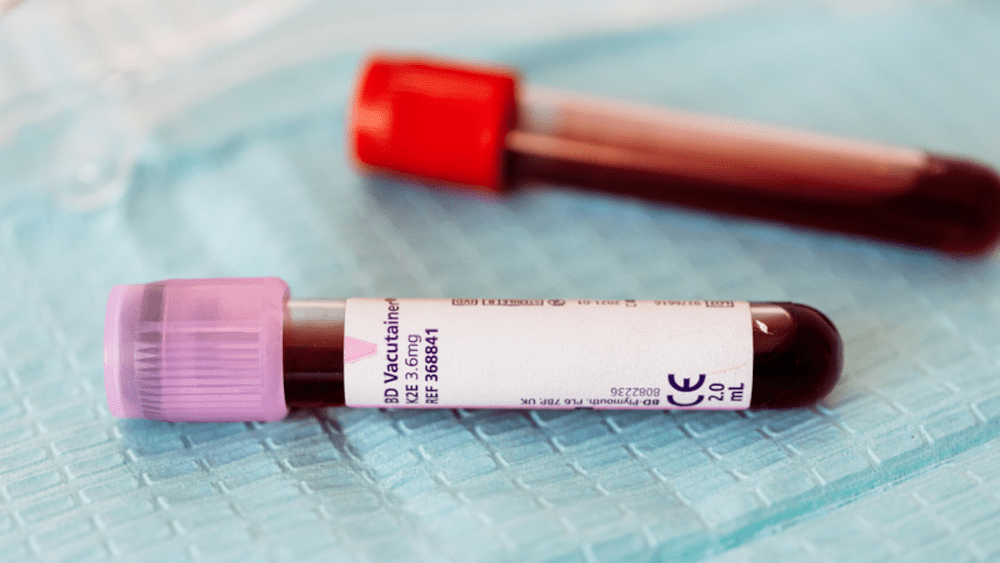
企業の健康診断で必ず受ける「血液検査」。身体のことを知るために重要な検査であることは分かっていても、実際にはどんなことがわかるのか、血液検査における「異常」がどれほど危険なものかは知らないという人事・総務部の担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回は血液検査の内容や結果の見方、血液検査で引っかかってしまった時の対応などをご紹介します。健康経営を推進していきたい企業や社内の健康情報を活用していきたい企業の人事・総務部の担当者や役職者の方は、ぜひこの記事を参考に、企業の健康経営を推進していきましょう。
健康診断の血液検査で何がわかるのか

血液検査は、採血をして身体の異常の有無や程度を調べる検査です。検査そのものはすぐに終わりますが、血液検査から得られる情報は多いです。
血液検査で分かること
血液検査と一口にいっても、その中には様々な検査内容が含まれています。
- ・一般血液検査
・生化学検査
一般血液検査では貧血や炎症などを知ることができ、生化学検査では腎臓・肝臓の異常、脂質異常症や糖尿病を疑うことができます。また、血液検査から生活習慣病のリスクを推測することもできます。
血液検査前日前夜はなぜ食事を抜くべきなのか
血液検査は、生活習慣による影響やその時の身体の異常や程度を調べますが、血液検査の前には食事を抜く(または指定された時間までに食事を終える)必要があります。
食べ物に含まれている糖質や脂質は、全身のエネルギー源となるために血管内に取り込まれます。そのため、食後は血液中の血糖や中性脂肪の値が上昇します。
食後に血液検査をして血糖や中性脂肪の数値が高い場合、元々数値が高い傾向にあるのか、食事の影響で高いのかの判断がつきません。正確な検査結果を得るために、血液検査前の絶食が推奨されています。
健康診断における血液検査の結果の見方と基準値
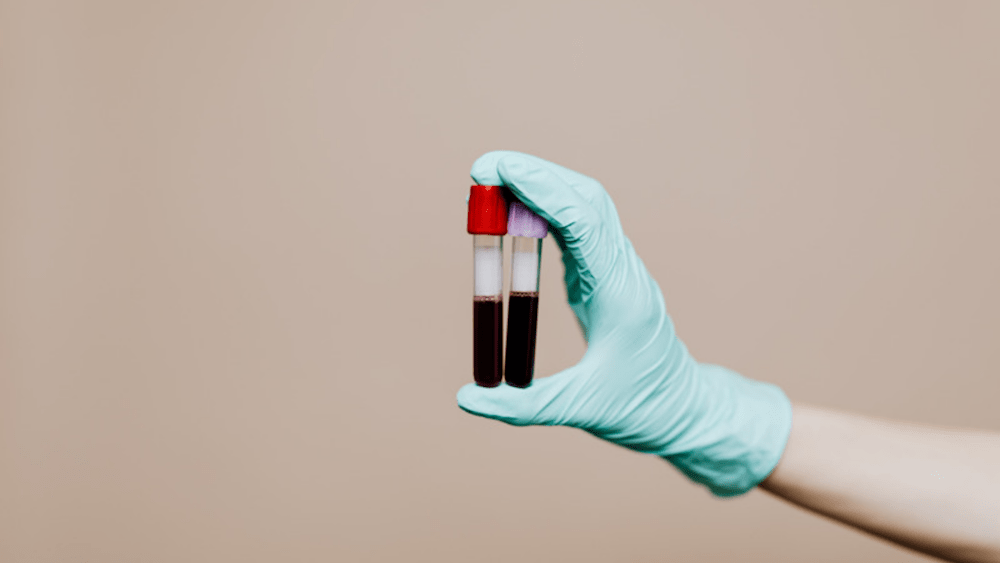
健康診断結果を受け取った後、自分でその数値を確認しようにも、どの項目がどういった意味なのか、基準値がどれくらいなのかもわかりにくいでしょう。ここでは、結果の見方とその基準値について、検査項目ごとに説明していきます。
一般血液検査
白血球数(WBC)
細菌などから身体を守っている白血球は、抗体を作ったり体内へ侵入してきた細菌などを捕食したりする役割を担っています。赤血球同様に多すぎても少なすぎてもよくありません。数値が高いと白血病・細菌感染症・骨髄増殖性疾患、数値が低いと薬剤アレルギー・再生不良性貧血・肝硬変・ビタミンB12欠乏性貧血などが疑われます。
なお、喫煙者は白血球数が多い傾向にあるとされています。
| 要医療 | 異常なし | 軽度異常 | 要経過観察 | 要医療 |
| 3.0以下 | 3.1~8.4 | 8.5~8.9 | 9.0~9.9 | 10.0以上 |
単位:10³/μL
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
血色素量(ヘモグロビン量、Hb)
貧血や出血、多血症を調べる検査で、ヘモグロビンの数が不足していれば貧血または出血が疑われます。逆に、ヘモグロビンの数が多すぎると多血症と判断されます。
| 要医療 | 要経過観察 | 異常なし | 軽度異常 | 要医療 | |
| 男性 | 12.0以下 | 12.1~13.0 | 13.1~16.3 | 16.4~18.0 | 18.1以上 |
| 女性 | 11.0以下 | 11.1~12.0 | 12.1~14.5 | 14.6~16.0 | 16.1以上 |
単位:g/dL
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
血小板数
出血したとき、血を止める役割を果たすのが血小板です。数値が低い場合は白血病や再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、肝硬変などが疑われます。数値が高い場合は、本態性血小板血症、慢性骨髄性白血病、鉄欠乏性貧血、慢性炎症などが考えられます。
| 要医療 | 要経過観察 | 軽度異常 | 異常なし | 軽度異常 | 要医療 |
| 9.9以下 | 10.0~12.2 | 12.3〜14.4 | 14.5〜32.9 | 33.0~39.9 | 40.0以上 |
単位:10⁴/μL
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
脂質検査
中性脂肪
過剰なエネルギーは中性脂肪として脂肪細胞や肝臓などに蓄えられます。数値が高いと動脈硬化や脂質異常症、脂肪肝、急性膵炎の原因になります。基準値より低ければいいというものではなく、数値が低いと肝硬変や低栄養などが疑われます。
| 要医療 | 異常なし | 軽度異常 | 要経過観察 | 要医療 |
| 29以下 | 30~149 | 150~299 | 300〜499 | 500以上 |
単位:㎎/dL
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
HDLコレステロール
HDLコレステロールは、いわゆる善玉コレステロールと呼ばれるものです。HDLコレステロールが少ないと、動脈硬化などの心血管系のリスクが高まります。「善玉」と言われているように、かつて、HDLコレステロールは多いほどよいとされてきましたが、コレステロール転送たんぱく欠損症によっても数値が高くなることもあることがわかっています。この症状は動脈硬化の原因となりうるため、数値が高いからよいというものでもありません。
| 要医療 | 要経過観察 | 異常なし |
| 34以下 | 35~39 | 40以上 |
単位:㎎/dL
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
LDLコレステロール
「善玉」であるHDLコレステロールに反して、LDLコレステロールは「悪玉」コレステロールと呼ばれるものです。LDLコレステロールの数値が高いと動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。また、数値が低いと脂質異常症(低LDL-C血症)の可能性があり、肝硬変・甲状腺機能亢進症・吸収不良・栄養障害などが疑われます。
| 要医療 | 異常なし | 軽度異常 | 要経過観察 | 要医療 |
| 59以下 | 60~119 | 120~139 | 140〜179 | 180以上 |
単位:㎎/dL
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
肝機能検査
AST(GOT)/ALT(GPT)
AST(GOT)は心筋や骨格筋、肝臓に多く存在する酵素で、ALT(GPT)は肝細胞に多く存在する酵素です。どちらも肝臓で異常があった場合に増加します。AST(GOT)とALT(GPT)のどちらの数値も高い場合は肝機能障害(脂肪肝・アルコール性肝炎・急性肝炎・慢性肝炎・肝臓がんなど)が疑われます。AST(GOT)の数値だけが高いのであれば、心筋梗塞や筋肉疾患などが疑われるでしょう。
| 異常なし | 軽度異常 | 要経過観察 | 要医療 | |
| AST(GOT) | 30以下 | 31~35 | 36〜50 | 51以上 |
| ALT(GPT) | 30以下 | 31~40 | 41〜50 | 51以上 |
単位:U/I
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
γ-GT(γ-GTP)
γ-GT(γ-GTP)は、肝臓や腎臓、すい臓、小腸などに含まれている酵素です。数値が高いとアルコール性肝障害・慢性肝炎・薬剤性肝障害・胆道炎が疑われます。
| 異常なし | 軽度異常 | 要経過観察 | 要医療 |
| 50以下 | 51~80 | 81〜100 | 101以上 |
単位:U/I
参考:日本人間ドック学会「判定区分 2021年度版」
糖尿病検査
空腹時血糖、HbA1c(NGSP)
血液中のブドウ糖がエネルギー源としてきちんと利用されているかを検査します。食後に上昇した血糖値が適切に低下するかを調べているため、10時間以上の絶食が必要です。空腹時血糖の数値が高いと、糖尿病・すい臓がん・ホルモン異常が疑われます。
| 異常なし | 軽度異常 | 要経過観察 | 要医療 |
| 空腹時血糖:99以下、かつHbA1c:5.5以下 | 下記①②のいずれか ①空腹時血糖:100〜109かつHbA1c:5.9以下 ②空腹時血糖:99以下かつHbA1c:5.6-5.9 |
下記①〜④のいずれか ①空腹時血糖:110〜125 ②HbA1c:6.0〜6.4 ③空腹時血糖:126以上かつHbA1c:6.4以下 ④空腹時血糖:125以下かつHbA1c:6.5以上 |
空腹時血糖:126以上かつHbA1c:6.5以上 |
健康診断の血液検査で異常が出たら
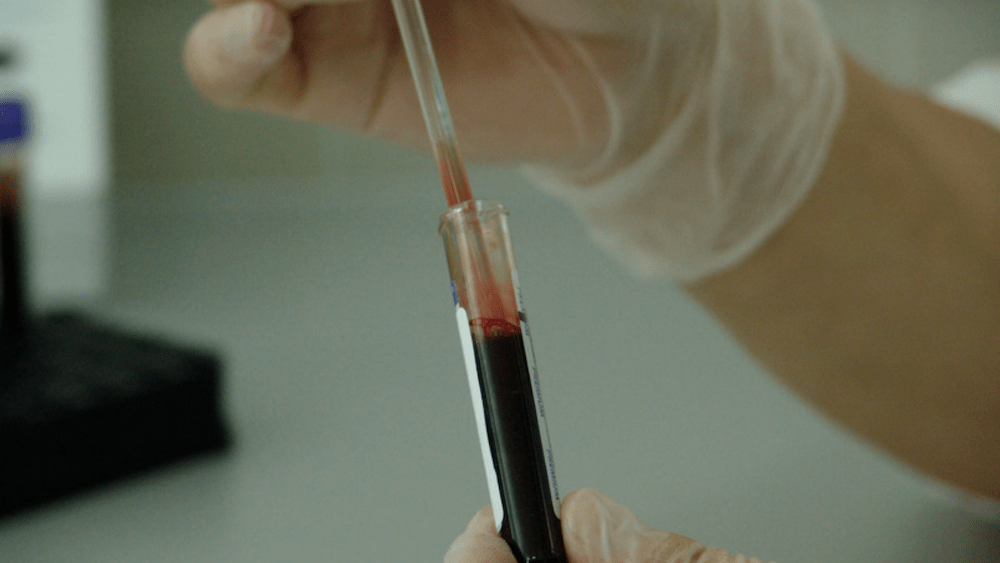
健診結果では、当然ながら「異常なし」が望ましいです。しかし、中には「要経過観察・要再検査」「要精密検査」「要治療」などと判断されることもあります。どれも注意が必要な状態ではあるものの、適切な対処は異なります。それぞれの判断の意味を知り、結果への対応を覚えておきましょう。
要経過観察
症状の進行や変化がないか、一定期間ごとに医療機関で経過をみることが必要です。病気の予防や健康維持を心がけてもらうようフォローをしていきましょう。要再検査
病気か否かの確認も含め、診断を確定するために同じ検査を再度おこなう必要があります。必ず受診勧奨をしましょう。
要精密検査
健康診断よりも詳しい検査を受けて診断を確定させることが必要です。必ず受診勧奨をしましょう。
要治療
明らかに病気と考えられるため、早急に治療が必要です。早急に専門医への受診を勧告してください。血液検査の結果はデータ化して管理すべき

血液検査でわかる生活習慣病は、自覚症状が現れる前に進行していることも多いです。基準値や過去の健診結果と比較できるようにし、管理しておくことが重要です。
そのため、管理が大変な紙よりも、データ保存が適しています。また、再検査や精密検査、治療を従業員に受けてもらうことも、健康経営を推進していく上で欠かせません。できるだけ早い対応が必要になるため、データをもとに従業員への受診勧奨がスムーズにできることも大切です。
企業の健康管理に特化したクラウド型健康管理システム『Growbase(旧:ヘルスサポートシステム)』なら、全従業員の健康情報を一元管理できます。健診データから受診勧奨対象者を簡単に見つけ出し、一括メール配信による受診勧奨で素早い対応が可能です。
シンプルな入力画面からデータ入力が行えるため、産業医にとっても意見書や紹介状の作成がスムーズになります。人事・総務部の担当者のみならず、従業員にとっても迅速な対処を行ってもらえることで、より健康への意識が強くなるでしょう。
※本ページで記載している「基準値」は、Growbaseスタンダード版と相違がある部分もございます。また、Growbaseスタンダード版では、「精密検査」の項目はございません。
Growbaseを導入することにより、健康管理業務にかかる時間や工数を削減することが可能です。組織全体の健康課題を可視化することで、早めのフォローを実施しやすくなります。
また、使いやすいUIと自由度の高い機能を備えており、個別・一括メール配信、面談記録、受診勧奨、部下状況、特殊健康診断の業務歴調査と管理、健診データ一元化、各種帳票出力(労基報告など)、ストレスチェック、長時間労働管理などの機能が充実しています。
以下で、Growbaseの詳細をご確認ください。
クラウド型健康管理システム「Growbase(グロウベース)」の詳細はこちら
まとめ
健康診断の血液検査は、従業員の健康状態を知るための大きなバロメーターです。食事制限が結果に影響するため、健康診断前には従業員へ注意を促すことを忘れないようにしましょう。<監修者プロフィール>
医師、公認心理師、産業医:大西良佳

医学博士、麻酔科医、上級睡眠健康指導士、セルフケアアドバイザー
北海道大学卒業後、救急・在宅医療・麻酔・緩和ケア・米国留学・公衆衛生大学院など幅広い経験からメディア監修、執筆、講演などの情報発信を行う。
現在はウェルビーイングな社会の実現に向けて合同会社ウェルビーイング経営を起業し、睡眠・運動・心理・食に関するセルフケアや女性のキャリアに関する講演や医療監修も行っている。
紙での健康診断運用を変えたい、
健康経営を目指しているご担当者さまへ
ウェルネス・コミュニケーションズでは、健診データをはじめとする社員の健康情報を一元管理することで企業と働く人の健康をサポートするクラウド型健康管理システム「Growbase」を提供しています。
企業毎に抱える課題はことなりますが、多くのご担当者さまも「何から始めていいかわからない」というのが現状です。
1,700社以上の導入実績のノウハウが詰まった資料を提供しております。ぜひ参考にしていただき、お役立ていただければと思います。
「Growbase」が1分でわかる
資料プレゼント
執筆者:Growbase編集部
健康診断の関連記事

健康診断の内容って?どんなことがわかる?3つの気になる疑問を解説
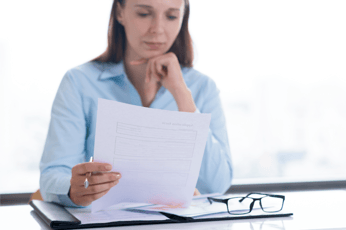
健康診断の結果の見方や管理する上で知っておくべきことをご紹介


